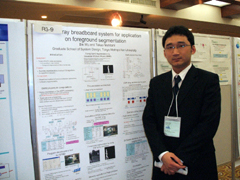| Japanese | English | |||||||||||||||||||||||||||
 第2号 2009年3月号
| |||||||||||||||||||||||||||
~消防技術研修(実施レポート)~
■指導者研修 In Tokyo
■救助技術研修 In Bangkok
また、1月29日から16日間にわたりタイ防災安全局アカデミーで開催された救助技術研修では、ユタナさんは教官として指導にあたりました。今回は、東京消防庁から5名と東京で学んだタイの防災安全局アカデミー4名、バンコク消防局の消防士1名、計5名が教官となり、60名の研修生に救助技術を伝授しました。訓練計画は、タイの教官と東京の教官の間で事前に綿密な打合せの上に作成しました。また、訓練が終わるとミーティングを行い、翌日の訓練内容について研修生の習熟度などを考慮し調整しました。ユタナ氏は、訓練計画の策定から実地における指導まで行いました。
アジア30億人のファッション市場は、今後拡大が見込まれる魅力的な市場です。世界に通用する若手ファッションデザイナーの発掘は、東京の存在感を一層高め、ビジネスチャンスを拡大するため、東京都の産業振興策の重要なテーマの一つになっています。
「新人デザイナーファッション大賞」は、アジア出身の未だブランドを立ち上げていない若手デザイナーを対象にした、世界最大級のコンテストです。今回は世界中から1万3千点もの応募がありました。 一次審査に残った30名のデザイナーは、3年間育成対象者として登録され、東京都が開催する育成セミナーへの参加、企業とのコラボレーション、展示会出展支援など様々なビジネス支援を受けることができます。 編集部では、受賞者による初の展示会を訪問し、本年、秀作賞を受賞した明ナミさんにインタビューを行いました。 Interview ソウルのデザイナー明さん
—ご自身のブランド・デザインのPRをお願いします
女性の体形を意識し、立ったり座ったりした時、美しく見える服作りを心がけ、常に新しいフォルムを探求しています。ベルギーの画家ルネ・マグリットに憧れ、受賞作品の着想も、彼の作品「モンマルトルの壁抜け男」から得たものです。—この展示会に出展した手ごたえは?
普段会うことのない、バイヤーやセレクト・ショップの方に作品を見ていただきました。予想以上にニットの作品を気に入ってもらえました。「もっと作品を見せてください」とか「もっとたくさん作品を作ってください」などと言われ、手ごたえを感じました。
取材後、このコンテストから世界へ羽ばたき活躍するアジアのファッションデザイナーが輩出する日も近いと感じました。明さんの受賞作品はこちらからご覧になれます。
http://www.fashion-gp.com/uk/2008/final-selection/index.html 同時に開催された「アジア9都市のファッションショー」の模様
 ジャンクショップ「ウォンパニ」 バンコクでは、タイ全体の人口の約10%の人々が生活する一方、廃棄物はタイ全体の24%を占めています。この1月に新知事に就任したスクムパン知事のもと、バンコク都は「廃棄物収集の効率化と廃棄物の最小化」を目標に、廃棄物の減量に取り組んでいます。 バンコクの廃棄物の特徴は、その約50%が食品廃棄物を中心とした有機廃棄物であるということです。有機廃棄物は分別が難しく、またリサイクルが困難であるという特徴があります。 これら有機廃棄物のほとんどは埋め立てられていますが、埋立地にも限界があり、現在コンポスト化(ごみを急速堆肥(たいひ)化装置などで肥料化すること)の推進が進められています。各家庭でのコンポストが広がりつつありますが、住民の廃棄物の適正処理への関心が高いとは言いがたく、地域コミュニティの中で、どのようにリサイクル意識を高めていくかが大きな課題となっています。 そういった中、バンコクの12のコミュニティで、コンポスト化を推進するためのパイロットプロジェクトが実施されています。これは、ひとつの村の中で、家庭から集めた有機廃棄物を分別し、堆肥化した上で、農業に利用するなどコミュニティの中で還元させるものです。つまり、一つのコミュニティの中で循環型の仕組みを完結させようという取組です。 また、有機廃棄物をコンポスト化する際に発生するメタンを、電気・熱エネルギーとして学校の調理に再利用し、学校教育の一環として取り入れている例もあります。 これらは住民を巻き込んだ形でのリサイクルを目指すバンコク都らしい試みといえます。 また民間の取組ではありますが、タイの最大手のリサイクル会社「ウォンパニ」の革新的な手法をご紹介します。この会社は、1974年に資源ごみを個人的に回収することからスタートしました。今では、タイ全土で300を超えるジャンクショップをフランチャイズ化し、リサイクル可能な廃棄物を市民から回収し、種類ごとに分別しています。リサイクル可能品目を明らかにし、変動する資源ごみの購入価格を店頭やインターネットで公開しています。
現在ウォンパニは、モデル事業者として、東南アジアの他の国々からも注目されています。バンコク都もこの活動に大いに注目しており、都職員をウォンパニに派遣し研修を受講させるほか、ウォンパニのようなジャンクショップをもっと増やし、地域の中でリサイクルができる仕組みを検討しています。
首都大学東京では、アジア地域を中心に、現在約200名の留学生を受入れ、アジア人材の育成に積極的に取り組んでいます。
今回は、中国からの留学生で、システムデザイン研究科情報通信システム工学専修修士2年、呉 斌(ご ひん)さんにお話をお伺いしました。呉さんは、大学1年生のときから首都大学東京で学んでいます。今年の4月からは、日本の企業に就職することが決まっています。 Interview 中国からの留学生 呉さん
—日本企業への就職が決まったとのことですが、就職活動はいかがでしたか。
留学当初から日本で働きたいという目標を持っていたので、初志貫徹ができました。研究内容を活かせる企業を8社ほど選び、大手企業だけでなく、中小企業も訪問しました。第一希望の会社へ就職が決まったときは非常に嬉しかったです。エントリーシートへの記載や面接における意思疎通には、困難を伴う部分もありましたが、何度も面接の練習をしたり大学の就職課を活用するなどしました。企業は、留学生であるかどうかではなく、その人材が企業にとって必要か否かを見ています。そういった意味で、留学生であることの壁は感じませんでした。 —将来の夢は?
第一志望の企業に就職することができたので、将来にわたり、決定した就職先で切磋琢磨して働きたいと思います。留学したからには、という使命感や親の理解もあり、現在のところ、母国へ戻る予定はありません。—首都大学東京への留学生またはこれから日本での留学を考えている方へのメッセージは?
最初に応接室で、中田清嗣常務にお話を伺いました。応接室に案内されると、まず目に入ったのが壁に掲げられたおびただしい特許の数でした。 「お客さんからの要望を聞き、営業の情報をもとに設計を中心に製品をつくっているうちに、特許に結びついたという感じ。一人ひとりの従業員が創意工夫してものづくりに取り組んだ結果です。」 これだけの技術、身につけるまでは大変なのでは。 「汎用旋盤を一通りマスターするには、最低でも3、4年が必要。奥が深いので、15年以上たっても学ぶことは多いのです。」やはり、一人前になるまでは大変だ…
さて、肝心のグローバル化の話に移ります。南武がタイに事業展開している話については、事前に調べてきましたが、国内工場でも、2名の中国出身の従業員を雇用している話をはじめて聞かされました。 「中国から来た2名のうち、一人はすでに10数年ほど勤めており、設計課長の職についています。もう一人は学校の先生を辞めて入社してきました。二人とも非常にしっかりした人物です。」 さらに、「うちは日本人従業員と外国人従業員を一切区別していません。給与体系もすべて同じです。」と常務は付け加えました。 海外からの来訪者も絶えることがありません。それこそ世界中から南武の技術を学ぼうとする人たちが訪れています。中には、南武の製品(50kg以上の重さ!)を購入し、両手で抱えて帰る人もいるそうです。 このように、世界中から注目される技術をもつ南武が、タイに工場をつくり、当初は日本人との気質の違いに戸惑いながらも、今や「南武の優等生」と呼ばれるまでになった話は次号でお伝えします。 | |||||||||||||||||||||||||||
| © Tokyo Metropolitan Government |