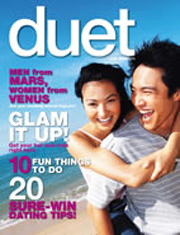| ANMC21会員都市が行う、先進的な取組を紹介していきます。
|
(1)FROM東京 ~3万5千人が駆け抜けた!東京マラソン2009~
今回で3回目となる東京マラソンは3月22日(日)に開催され、EXPOなど様々なスポーツ関連イベントとあわせて盛大に行われました。
今年は、10kmとフルマラソンとを合わせて3万5千人(昨年より5千人増)の定員枠に対して、応募者数は約26万人にも及びました。また、海外からも約70カ国から約2,700人がランナーとして参加するなど、国内外から非常に高い人気を博した大会となりました。
マラソン当日は、国際的なトップアスリートをはじめ、オリンピック招致をPRするために北京オリンピックレスリングでメダルを獲得した伊調姉妹などのゲストランナーも多数参加し、会場は大変盛況でした。レース途中から時折雨が降る悪天候ではありましたが、97%もの方々が完走を果たしました。
初めて大会に参加したアジアのランナーの方にレース後に感想を伺ったところ、走行中は、プーさんの着ぐるみを着たランナーや、面白い帽子を被ったり天使の羽をつけて走る子どものランナーなど、ちゃめっけのある走者との遭遇が印象に残った、とのことでした。また、大勢のボランティア(総勢約13,000人)によるコースの誘導や、食料の配給が大変充実しており、沿道からの温かい声援も走っていて非常に嬉しかったようです。
4回目を迎える来年も、国内外のランナーにとってそれぞれ素敵な思い出となるようなマラソン大会になることを願っています。
|

紙吹雪の中、ランナーが一斉にスタート! |

銀座を疾走するランナー |
(2)FROMシンガポール ~シンガポールのユニークな少子化対策
少子化問題は、労働力、年金問題などと密接につながっており、近い将来アジアの大半の国が直面する重要な課題です。今回は編集部が選んだシンガポールのユニークな少子化対策を紹介します。
シンガポールでは、2004年に合計特殊出生率が1.26まで低下しましたが、近年は回復の兆しが見えてきました(2007年1.29)。しかし、人口増加につながる目標の2.1にはまだ遠い状況です。
昨年の建国記念日の施政方針演説で、リー首相は、概ね半分の時間を少子化対策に費やし、自らの体験を織り交ぜ、国民にこの問題への理解と協力を呼びかけたほどです。
|
中でもユニークなのは、結婚支援策です。民間会社ではなく、政府が直接、独身男女を対象に、会員制の「Love Byte」という出会い系サイト(http://www.lovebyte.org.sg) を設け、趣味や地縁によるサークル活動を誘導し、婚姻率の上昇を図る取組みを行っています。サイトの会員ページには「出会いを確実につかむコツ」や「デート時の服装」といったノウハウが掲載され、めでたくゴールインしたカップルの体験談も多数載っています。
このほか、季刊の情報誌「DUET」を発行して、デートの際に使える割引クーポンや流行スポット、交流パーティーなどの各種イベントスケジュールなどを掲載しています。登録している独身男女が安心できる出会いの場で生涯の伴侶を見つけられるよう、強力にバックアップしています。
|
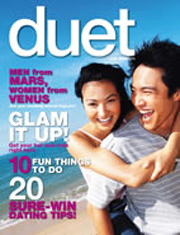
情報誌「DUET」
|
さらに、結婚の次は、夫婦が出産や育児をし易い環境づくりが重要と、政府はこちらに対する優遇策も強化しました。
たとえば、子ども一人につき、「子育て口座」という専用の特別口座が開設され、親が貯金すると同額の補助金が政府から口座に支給されるという制度が新たに設けられました。上限はありますが、政府が認可する保育所や幼稚園、教育機関などへの支払に使えるなど、かさむ教育費に頭が痛い親達にとって救世主になりそうです。
|